近年、マンションやアパートだけでなく、一戸建てでも鉄骨造を選ぶ方が増えています。
しかし、鉄骨造の防音性については、不安を抱く方も少なくないでしょう。
隣の音、上の階からの足音…気になる生活音は、快適な暮らしを大きく左右します。
今回は、鉄骨造(S造)の防音性について、構造の違いや具体的な防音対策を分かりやすくご紹介します。
賃貸住宅と持ち家、それぞれに合った対策も解説しますので、ぜひ最後までお読みください。

鉄骨造S造の防音性とは
軽量鉄骨造と重量鉄骨造の違い
鉄骨造には、鋼材の厚さによって「軽量鉄骨造」と「重量鉄骨造」の2種類があります。
軽量鉄骨造は鋼材の厚さが6ミリ未満、重量鉄骨造は6ミリ以上と定義されています。
軽量鉄骨造は、比較的低層の住宅や賃貸物件に多く用いられ、コストを抑えられるメリットがあります。
一方で、重量鉄骨造は高層ビルやマンションなど、強度が求められる建物に使用されます。
防音性については、重量鉄骨造の方が軽量鉄骨造よりも優れていますが、どちらも鉄筋コンクリート造と比べると低いと言えます。
軽量鉄骨造は、木造軸組構造の鉄骨版のような構造で、プレハブ工法が多く用いられます。
重量鉄骨造は、柱と梁で建物を支えるラーメン構造が一般的です。
鉄骨造と他の構造物の防音性の比較 木造RC造との違い
鉄骨造の防音性は、木造よりは高いものの、鉄筋コンクリート造(RC造)や鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)には劣ります。
RC造はコンクリートの厚みによって遮音性が大きく変わるため、RC造のマンションは鉄骨造よりも防音性に優れていることが多いです。
木造は、鉄骨造やRC造に比べて遮音性が低く、防音対策が重要になります。
これらの構造の違いは、音の伝わりやすさや遮断性能に影響を与え、居住者の快適性に大きく関わってきます。
鉄骨造S造の防音性の弱点と改善策
鉄骨造の防音性の弱点は、主に軽量な素材と、コンクリートを使用しない構造にあります。
音は空気中を伝わるだけでなく、建物の躯体(柱や梁など)を伝わって伝播するため、躯体の材質や構造が防音性に大きく影響します。
改善策としては、後述する防音対策が有効です。
特に、床や壁、窓への対策が重要となります。

鉄骨造S造 防音対策徹底ガイド
賃貸住宅での効果的な防音対策
賃貸住宅では、大規模な工事は難しい場合が多いです。
そのため、防音マットや厚手のカーペット、防音カーテンなどの利用が効果的です。
防音マットは、床への衝撃音を軽減し、下階への騒音トラブルを防ぐのに役立ちます。
防音カーテンは、窓からの音漏れを防ぎ、外部からの騒音を軽減する効果があります。
また、家具の配置にも注意し、壁から離して配置することで、音の反響を減らすことができます。
持ち家での効果的な防音対策 床天井壁窓
持ち家であれば、より本格的な防音対策を行うことができます。
床には、コンクリートスラブや遮音性の高い床材を使用することで、足音などの振動を抑制できます。
天井には、吸音材を充填することで、上階からの音を吸収することができます。
壁には、二重構造にする、または厚みのある遮音材を使用することで、隣室からの音を遮断する効果を高めることができます。
窓には、二重サッシや防音窓を取り付けることで、外部からの騒音を大幅に軽減できます。
防音材選びのポイントと注意点
防音材を選ぶ際には、遮音性能(音を遮断する能力)と吸音性能(音を吸収する能力)に注目しましょう。
遮音性能は、遮音等級(L等級など)で表示されている場合が多いです。
吸音性能は、素材や厚さによって異なります。
また、施工方法も重要です。
隙間なく施工することで、防音効果を高めることができます。
防音材は、種類や性能によって価格が大きく異なるため、予算に合わせて適切な製品を選びましょう。

まとめ
鉄骨造(S造)の防音性は、木造よりは高いものの、RC造などに比べると劣ります。
軽量鉄骨造と重量鉄骨造では、重量鉄骨造の方が防音性に優れています。
賃貸住宅と持ち家では、できる防音対策に違いがあります。
効果的な防音対策には、床・壁・窓への適切な施工と防音材の選定が重要です。
生活音に配慮し、快適な住環境を築きましょう。


 0799-24-0558
0799-24-0558
 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
 ご来店予約
ご来店予約
 モデルハウス見学
モデルハウス見学





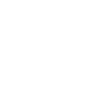
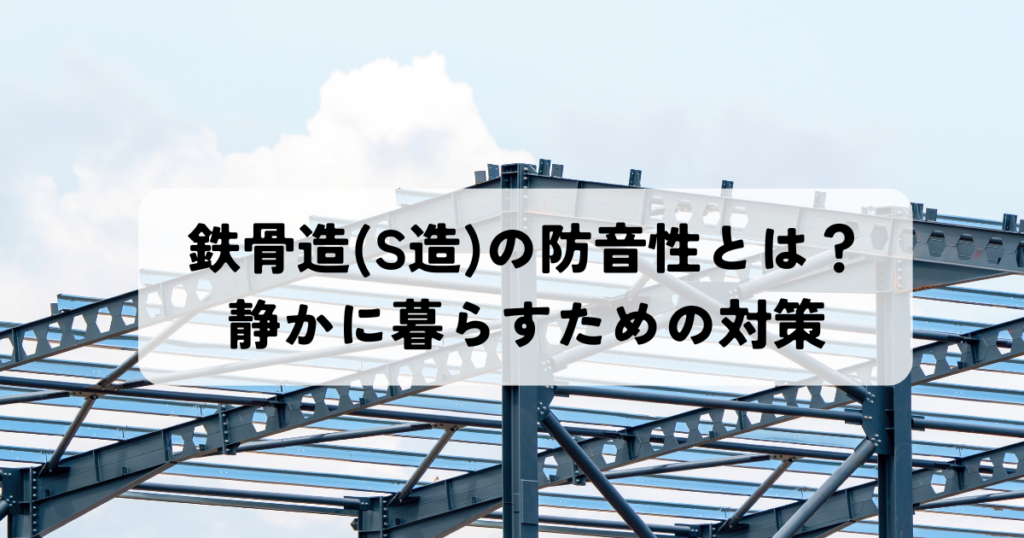
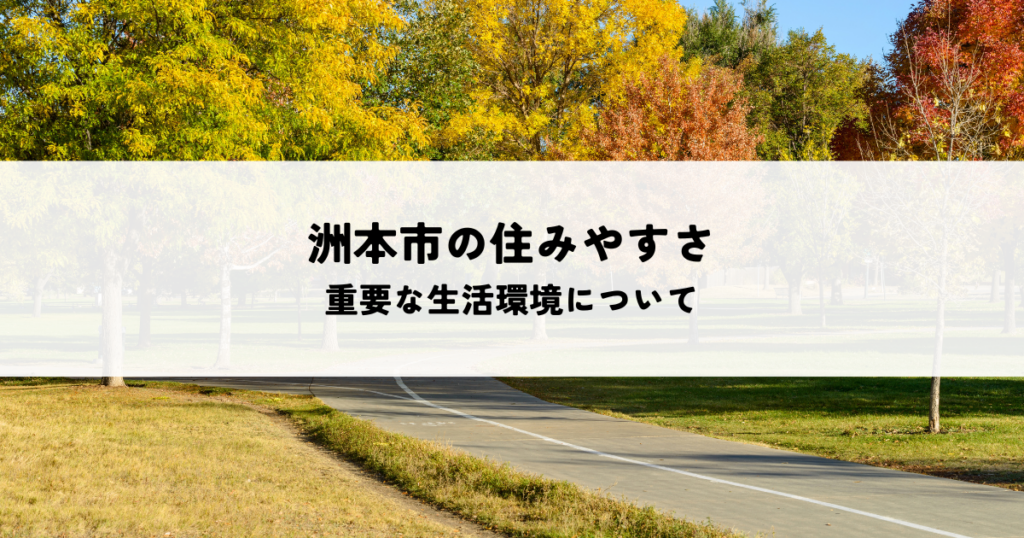
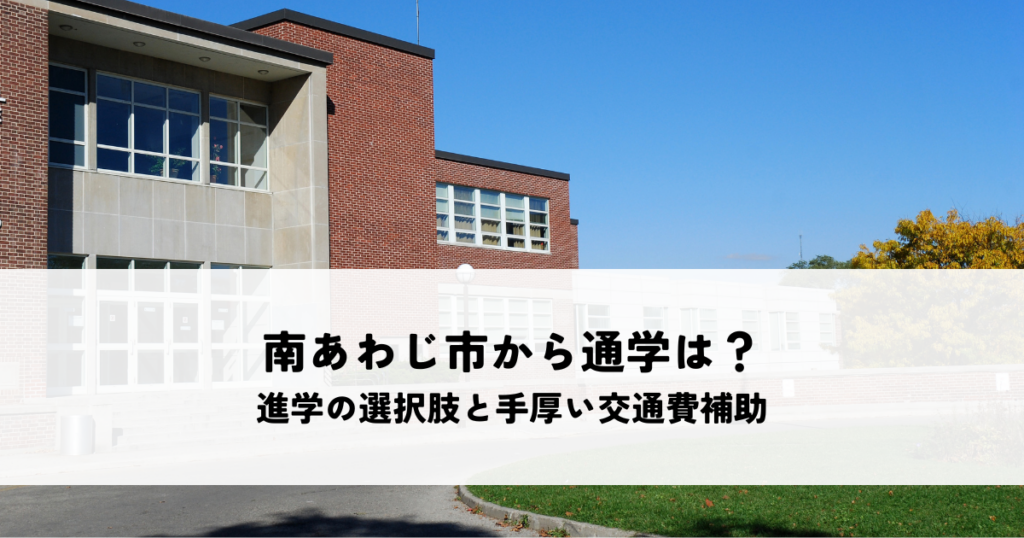
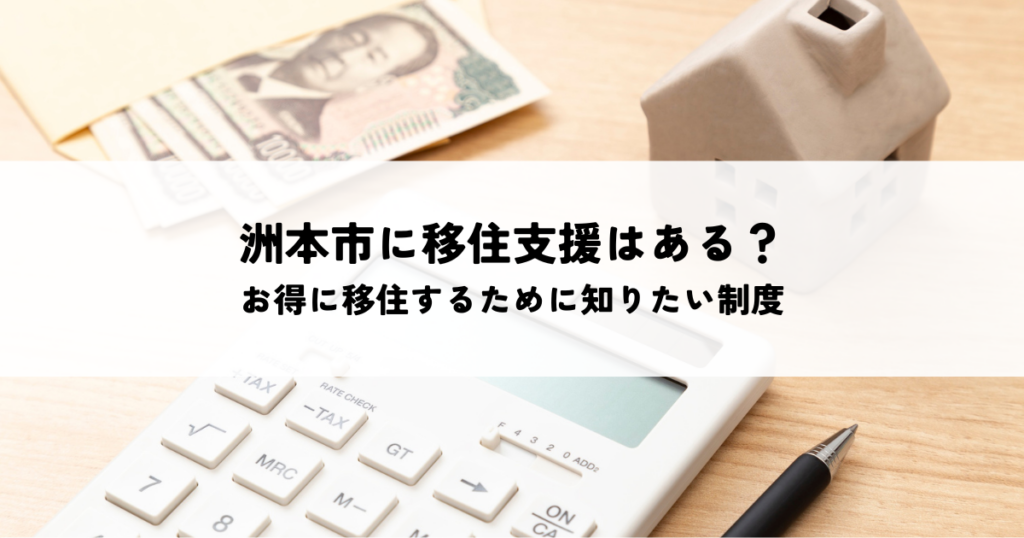
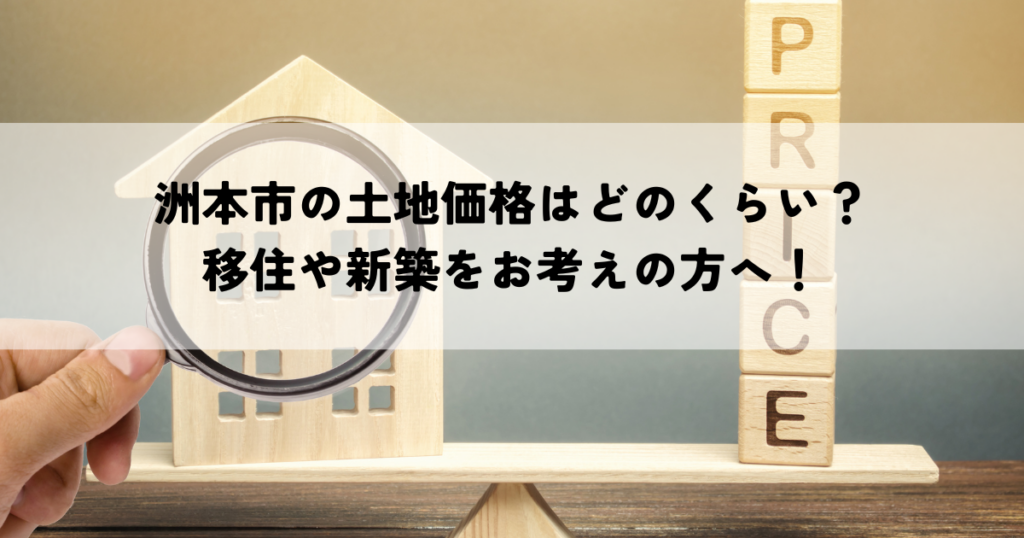

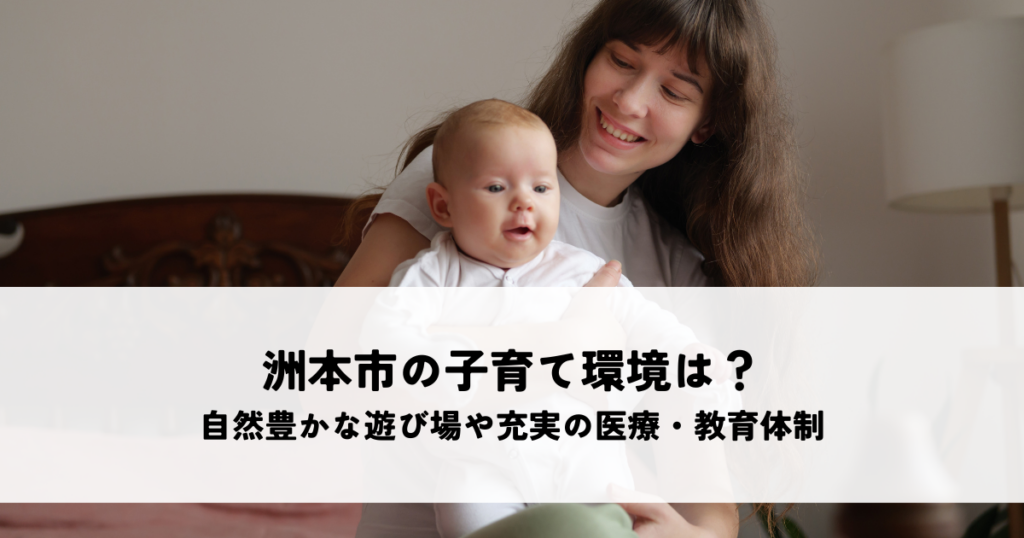
 イベント情報
イベント情報
 資料請求
資料請求
 お電話で
お電話で