一戸建てを購入検討中の方、あるいは既に所有していて固定資産税の計算方法に頭を悩ませている方にとって、税金は大きな関心事でしょう。
毎年の税負担を把握し、賢く税金対策をすることは、家計管理において非常に重要です。
今回は、一戸建ての固定資産税に関する情報を分かりやすくご紹介します。

固定資産税 シミュレーションで賢く税金対策
固定資産税の基礎知識
固定資産税は、毎年1月1日時点で土地や建物を所有している人が、その所在する市区町村に支払う税金です。
課税対象となるのは土地、建物、償却資産(事業用機械など)ですが、一戸建ての場合、土地と建物の固定資産税が主な対象となります。
納付は通常4月~6月頃に納税通知書が届き、一括または分割で支払います。
税率は標準税率1.4%ですが、自治体によって異なる場合がありますので、必ずご自身の地域の税率を確認してください。
固定資産税の計算方法
固定資産税の計算は、以下の式で行います。
固定資産税評価額(課税標準額)× 税率
まず、土地と建物の固定資産税評価額をそれぞれ算出します。
中古住宅の場合は、既に評価額が算出されているので、納税通知書や固定資産課税台帳で確認できます。
不動産会社に問い合わせるのも有効な手段です。
新築住宅の場合は、完成後に自治体による調査が行われ、評価額が決定されます。
概算値としては、土地は公示価格の70%程度、建物は建築費の50~60%程度が目安となります。
建物については、築年数に応じた経年減価補正率を乗じて評価額を算出します。
この評価額に税率を掛け合わせることで、固定資産税額が算出されます。
土地と建物の評価額の算出方法
土地の評価額は、公示価格や地価公示価格を参考に、70%程度を目安に算出します。
ただし、立地条件や地盤状況などによって変動します。
建物の評価額は、新築の場合は建築費の50~60%を目安としますが、築年数や構造、設備によって異なります。
築年数が経過している場合は、経年減価補正率を用いて、再建築価格から減価償却後の価格を算出します。
この減価補正率は、建物の構造(木造・非木造)や築年数によって異なります。
一戸建て固定資産税シミュレーション例1 新築住宅
例:土地価格2,000万円、建物価格3,000万円、土地面積100平方メートル、建物面積100平方メートル、税率1.4%、住宅用地特例・新築住宅特例適用
土地:2,000万円 × 70% × 1/6 × 1.4% ≒ 3.27万円
建物:3,000万円 × 60% × 1/2 × 1.4% ≒ 12.6万円
合計:約15.87万円
一戸建て固定資産税シミュレーション例2 築10年住宅
例:土地価格2,000万円、建物価格3,000万円、土地面積100㎡、建物面積100㎡、税率1.4%、築10年、住宅用地特例適用、経年減価補正率(木造)0.5
土地:2,000万円 × 70% × 1/6 × 1.4% ≒ 3.27万円
建物:3,000万円 × 60% × 0.5 × 1.4% ≒ 6.3万円
合計:約9.57万円
一戸建て固定資産税シミュレーション例3 更地
例:土地価格2,000万円、土地面積100平方メートル、税率1.4%
土地:2,000万円 × 70% × 1.4% ≒ 19.6万円

固定資産税軽減措置を徹底解説
住宅用地特例
住宅用地(居住用住宅の敷地)は、一定の面積まで課税標準額が軽減されます。
200平方メートルまでは1/6、200平方メートルを超える部分は1/3に軽減されます。
ただし、1月1日時点で住宅が完成していない場合は適用されません。
新築住宅特例
新築住宅(床面積50平方メートル以上280平方メートル以下)には、新築後3年間(長期優良住宅は5年間)、建物部分の固定資産税が1/2に軽減される措置があります。
これも、適用条件がありますので、必ず確認が必要です。
その他軽減措置
自治体によっては、独自の軽減措置を設けている場合があります。
詳細は、お住まいの市区町村の役所に確認してください。
軽減措置の申請方法
軽減措置を受けるには、申請が必要です。
必要な書類や申請期限は自治体によって異なりますので、事前に確認し、期限までに申請手続きを完了するようにしてください。

まとめ
今回は、一戸建ての固定資産税の計算方法、シミュレーション例、軽減措置について解説しました。
固定資産税は、土地と建物の評価額、税率、そして適用される軽減措置によって大きく変動します。
正確な金額を把握するためには、ご自身の土地と建物の状況、そして地域の税率を正確に把握し、必要に応じて専門家への相談も検討しましょう。
軽減措置の活用も忘れず、賢く税金対策を行いましょう。
この記事が、みなさんの税金対策の一助となれば幸いです。
なお、税制は変更される可能性がありますので、最新の情報を確認することをお勧めします。


 0799-24-0558
0799-24-0558
 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
 ご来店予約
ご来店予約
 モデルハウス見学
モデルハウス見学





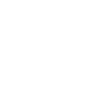

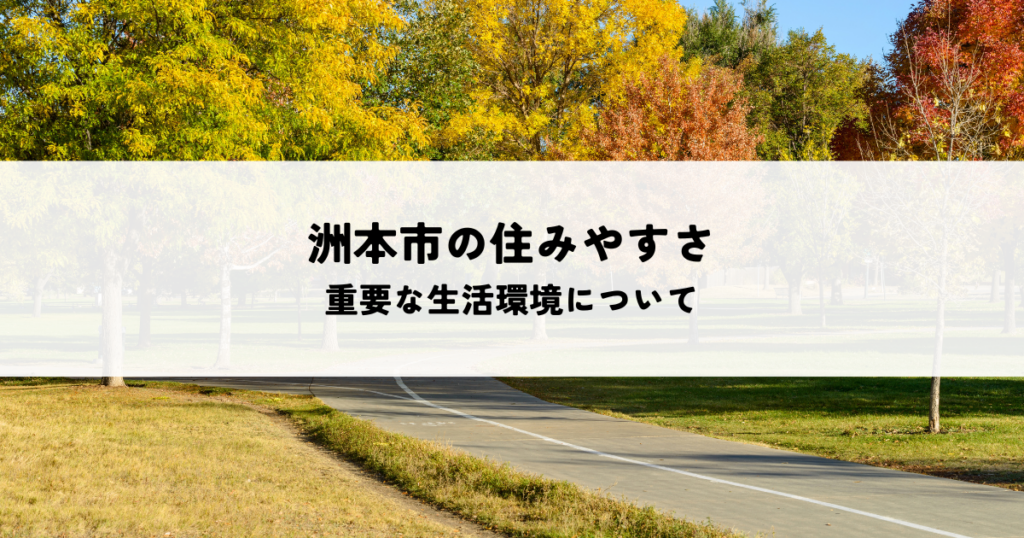
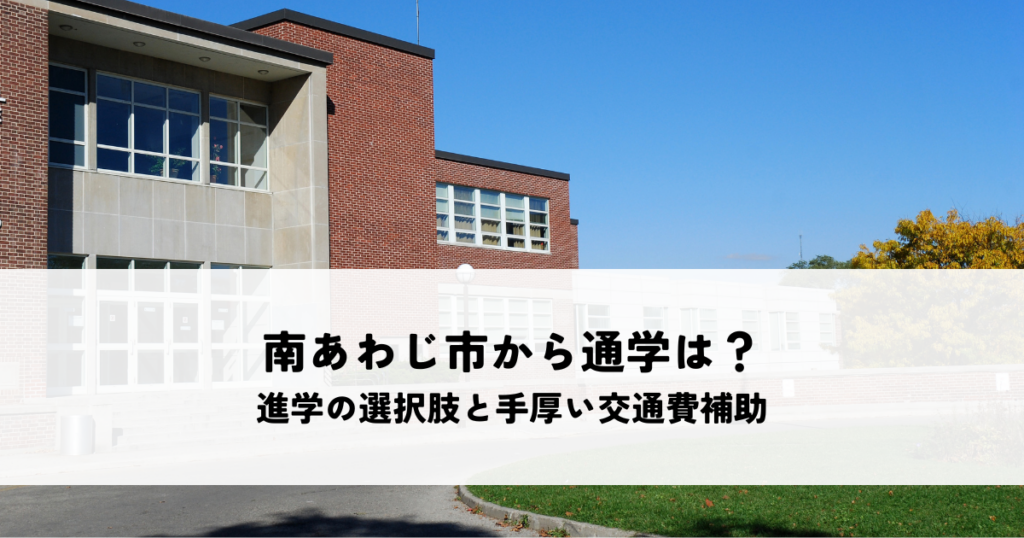
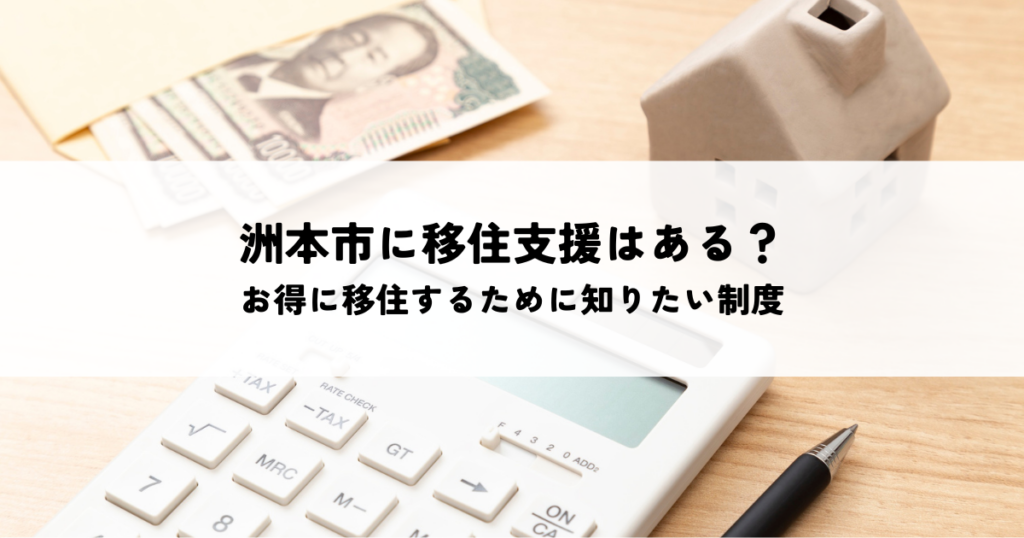
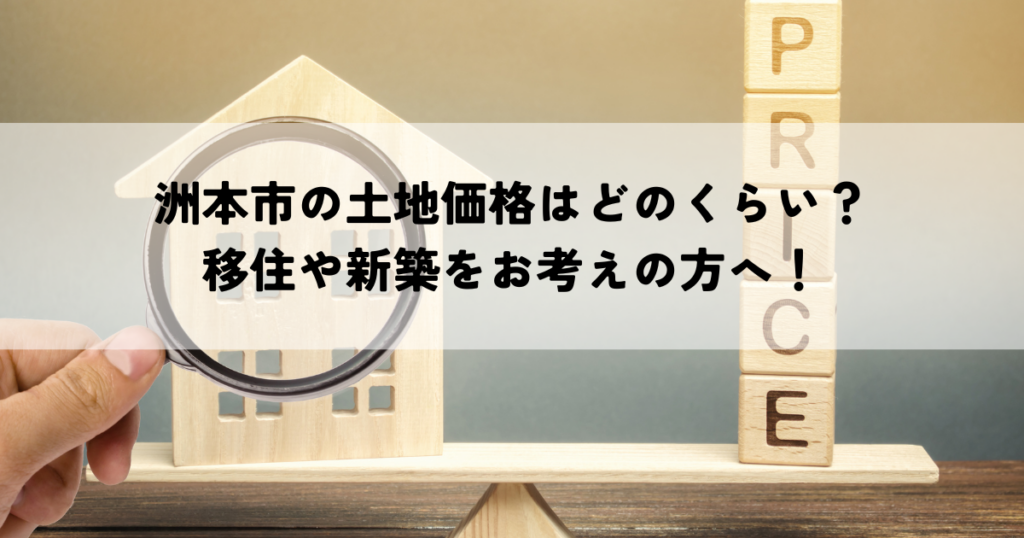

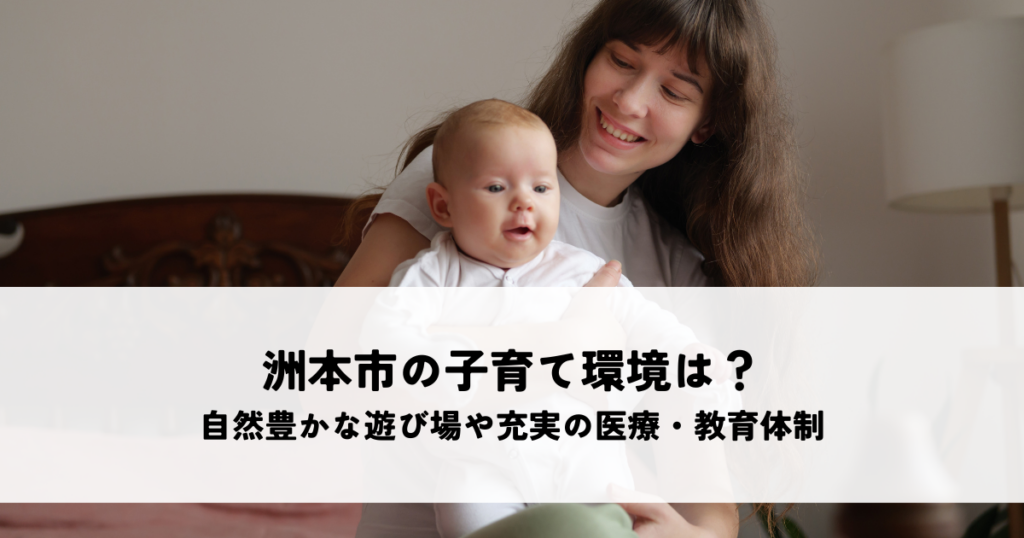
 イベント情報
イベント情報
 資料請求
資料請求
 お電話で
お電話で