外壁の素材選びは、家の印象を大きく左右します。
特に、近年人気の高い外壁サイディングは、種類や特徴、メンテナンス方法など、様々な点で選択肢が豊富です。
初めて外壁材を選ぶ方にとって、どの素材を選べば良いのか迷ってしまうのも当然のことでしょう。
今回は、外壁サイディングとは何か、その種類や特徴、選び方、そしてメンテナンス方法まで、分かりやすく解説します。
新築やリフォームを検討されている方の参考になれば幸いです。

外壁サイディングとは何か 種類と特徴を徹底解説
外壁サイディングの定義と歴史
外壁サイディングとは、建物の外壁に使用する仕上げ用の板材です。
パネル状のサイディングボードを建物の骨格に貼り付けることで、外壁を形成します。
モルタル外壁が主流だった時代から、その簡便な施工性とデザイン性の豊富さから、1960年代後半から普及が進み、現在では日本の住宅外壁材として圧倒的なシェアを誇ります。
窯業系サイディングの特徴
窯業系サイディングは、セメントと繊維質を主原料とするサイディングで、住宅外壁材のシェアの約70~80%を占める最も一般的な種類です。
セメントを使用しているため、耐久性が高く、衝撃や火にも強いのが特徴です。
レンガ調や石積み調など、デザインのバリエーションも豊富で、さまざまな住宅デザインに対応できます。
一方で、蓄熱しやすいという性質があるため、夏場の暑さ対策として断熱塗料などを用いたメンテナンスが必要となる場合があります。
金属系サイディングの特徴
金属系サイディングは、ガルバリウム鋼板などの金属を成型したサイディングです。
裏打材に断熱材を使用している製品も多く、断熱性が高いのが特徴です。
また、軽量で、モルタルの約1/10の重さしかないため、建物の負担を軽減し、耐震性向上にも貢献します。
錆びにくい素材を使用しているため、長期間にわたってメンテナンスの手間が少ないのもメリットです。
しかし、デザインは比較的シンプルで、窯業系サイディングのような多様なデザイン性を求める方には不向きな場合があります。
木質系サイディングの特徴
木質系サイディングは、天然木に塗装を施したサイディングです。
天然木の温かみのある風合いが魅力で、独特の高級感を演出できます。
しかし、天然木は水に弱いため、耐火性や耐水性において他のサイディングに劣る点がデメリットです。
そのため、こまめなメンテナンスが必要です。
近年では、木目調の窯業系サイディングなど、天然木に似たデザインと耐久性を両立した製品も多く登場しています。
樹脂系サイディングの特徴
樹脂系サイディングは、塩化ビニル樹脂を主原料とするサイディングで、北米では高いシェアを誇ります。
軽量で撥水性に優れ、耐久性や耐候性にも優れています。
しかし、日本ではまだ普及率が低く、デザインのバリエーションも少ないのが現状です。

外壁サイディングの選び方とメンテナンス方法
サイディング選びのポイント
サイディングを選ぶ際には、デザイン性、耐久性、価格、メンテナンス性などを総合的に考慮することが重要です。
家のデザインや予算、ライフスタイルなどを考慮し、最適なサイディングを選びましょう。
また、施工業者との相談も欠かせません。
外壁サイディングの耐用年数
サイディング自体の耐用年数は、種類によって多少異なりますが、一般的には40年程度と言われています。
しかし、塗料やシーリング材の劣化は5~10年程度で発生するため、定期的なメンテナンスが必要です。
必要なメンテナンスと費用
必要なメンテナンスは、シーリング材の打ち替え、塗装、部分的な張り替えなどです。
費用は、家の大きさ、使用する材料、施工方法などによって大きく異なります。
目安として、塗装の場合、2階建て住宅で約100万円~150万円程度です。
定期的な点検と早めの対処の重要性
定期的な点検と早めの対処は、サイディングの寿命を延ばし、高額な修理費用を避けるために非常に重要です。
年に一度は、自分で外壁の状態をチェックし、異常が見つかった場合は、専門業者に相談しましょう。
チョーキング(白亜化現象)やひび割れ、シーリング材の劣化などは、早めの対処が大切です。

まとめ
外壁サイディングは、種類、デザイン、耐久性、メンテナンス性など多様な選択肢があり、新築やリフォームの際に重要な選択となります。
窯業系、金属系、木質系、樹脂系とそれぞれにメリット・デメリットがあるため、自身の住宅の状況や予算、好みなどを考慮して最適なものを選ぶことが大切です。
定期的な点検と適切なメンテナンスを行うことで、サイディングの寿命を長く保ち、建物の美観と資産価値を維持することができます。
早めのメンテナンスは、高額な修繕費用を防ぐためにも有効です。
専門業者への相談も積極的に行い、安心して快適な住まいを長く保ちましょう。

 0799-24-0558
0799-24-0558
 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
 ご来店予約
ご来店予約
 モデルハウス見学
モデルハウス見学





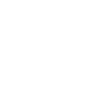


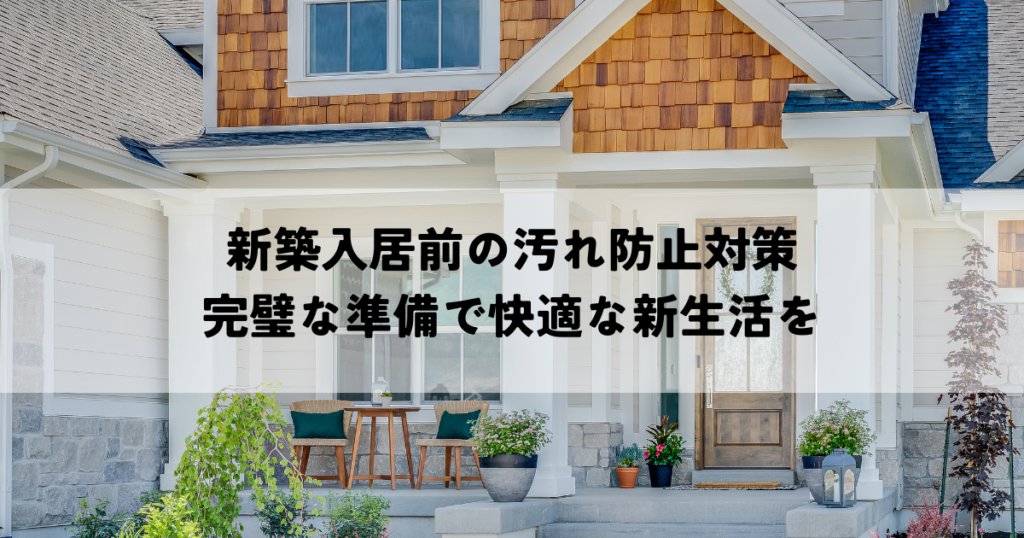
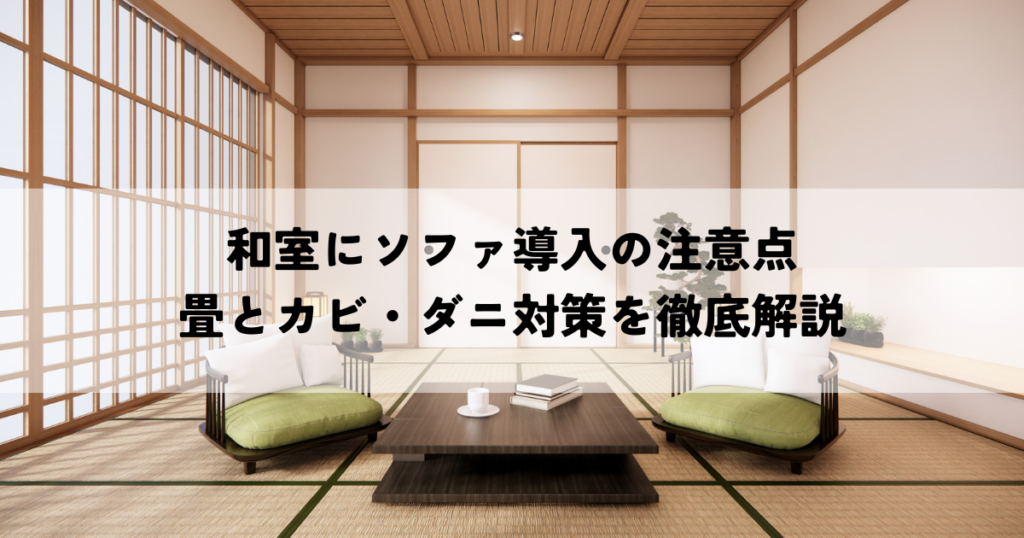
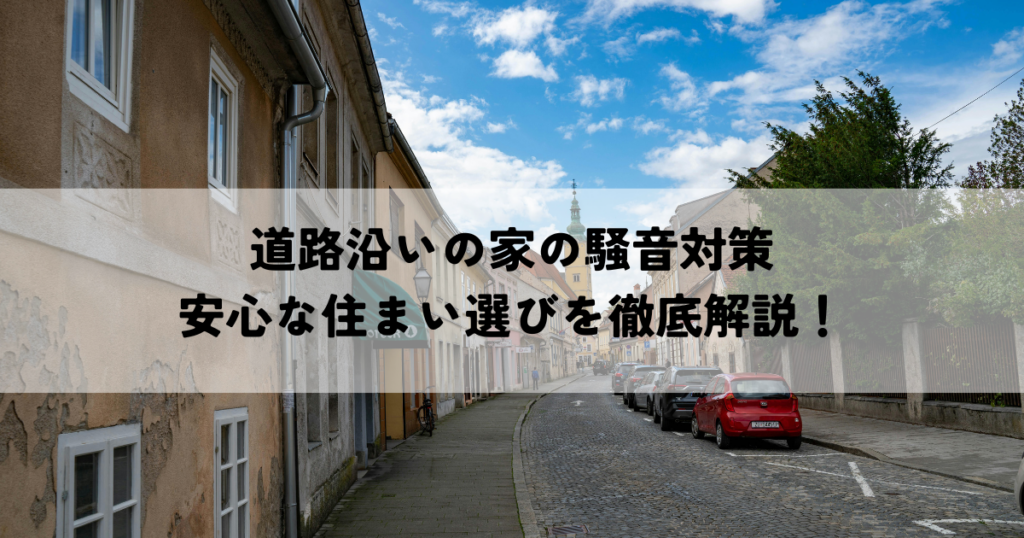


 イベント情報
イベント情報
 資料請求
資料請求
 お電話で
お電話で