地震に強い家を求めて、これから家を建て替えたり、新築を検討したりする方は多いのではないでしょうか。
地震はいつどこで起きるかわからない自然災害であり、大切な家族を守るためには、地震に強い住まいを選ぶことが重要です。
本記事では、地震に強い家の特徴を7つ紹介し、地震への備えを万端にするための知識と情報を提供します。

地震に強い家を建てる2つの理由
日本では、地震のリスクが常に存在するため、地震に強い家は必要不可欠です。
なぜなら、巨大地震はいつどこで起きるかわからないというリスクがあることと、建築基準法で耐震性が求められるからです。
1: 巨大地震のリスク
日本では、世界で発生するマグニチュード6以上の地震の約2割が発生していると言われています。
つまり、日本で暮らす以上は、巨大地震のリスクと向き合わざるを得ないのです。
過去の地震では、築年数の長い住宅の多くが倒壊し、大きな被害をもたらしました。
これから家を建てる際には、耐震性を最優先に考える必要があります。
2: 建築基準法の耐震基準
日本の建物は、建築基準法で定められた耐震基準を満たす必要があります。
耐震基準は、過去の大地震を教訓に、常に強化されてきました。
現在の耐震基準は、1995年の阪神淡路大震災を機に見直されたもので、震度6強から7の揺れでも倒壊しない強度が求められています。
この基準を満たすことで、地震発生時の被害を最小限に抑えることができます。
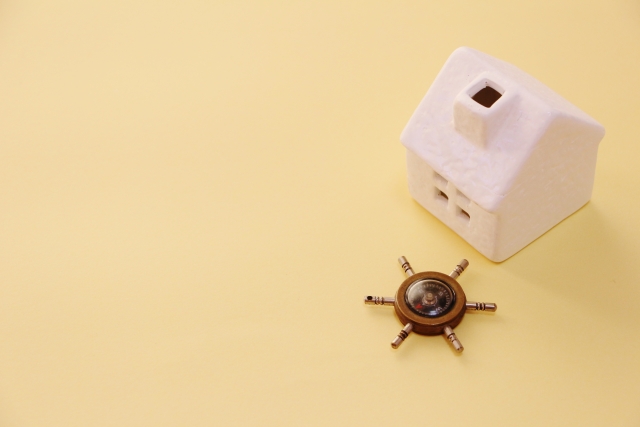
地震に強い家の7つの特徴
地震に強い家には、具体的な特徴がいくつかあります。
これらの特徴を理解することで、地震に強い家を建てるための判断材料となります。
1: 家の形が正方形・長方形になっている
地震が発生すると、揺れによって家に歪みが生じます。
複雑な形状の建物では、地震の揺れが予測しにくい形で伝わり、建物全体のバランスが崩れる可能性があります。
一方、正方形や長方形のシンプルな形状の家は、地震の揺れを建物全体に均等に分散させることができます。
そのため、一部の柱や壁に過度な負荷がかかるのを防ぎ、建物の強度を保つことが可能です。
2: 制震・免震対策を取っている
制震と免震は、地震の揺れに対する対策の1つです。
・制震
制震は、建物内にダンパーと呼ばれる装置を設置し、地震の揺れを吸収する考え方です。
ダンパーは、地震の揺れを吸収することで、建物の揺れを抑え、倒壊や損傷を最小限に抑えます。
・免震
免震は、建物の基礎と底の間に免震装置を挟むことで、地震の揺れを建物に伝えないようにする考え方です。
免震装置は、地震の揺れを吸収し、建物の揺れを大幅に軽減します。
制震・免震対策は、地震発生時の揺れを軽減し、建物の被害を最小限に抑える効果があります。
3: 周辺の地盤が強い
地盤の強さは、地震時の建物の安定性に大きく影響します。
軟弱な地盤は、地震の揺れによって液状化が発生する可能性があり、建物の倒壊や傾斜を引き起こす危険性があります。
そのため、地盤調査を行い、地盤の強度を確認することが重要です。
4: 築年数が新しい
築年数が古い建物は、現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。
耐震基準は、時代とともに強化されてきたため、古い建物は地震に対して脆弱な場合があります。
そのため、古い建物を改修する場合は、耐震補強工事を行う必要があります。
5: 平屋建てである
平屋建ての建物は、地震時の揺れに対する強度が高いため、地震に強いと言われています。
これは、平屋建ての建物は、構造がシンプルで、揺れが伝わりにくいからです。
また、階数が増えるほど、地震時の揺れは大きくなるため、地震に強い家を建てるためには、平屋建てを検討するのも良いでしょう。
6: 屋根に軽量な材料を使っている
屋根は、地震時に大きな揺れを受けやすい部分です。
そのため、屋根に軽量な材料を使用することで、地震時の被害を軽減することができます。
軽量な屋根材には、瓦や金属板などがあります。
7: 定期的にメンテナンスを実施している
建物の定期的なメンテナンスは、地震に強い家を維持するために不可欠です。
メンテナンスを行うことで、建物の劣化を防ぎ、地震に強い状態を保つことができます。
特に、地震に強い家の構造や設備は、定期的な点検が必要です。

まとめ
地震に強い家を建てるには、建物の構造、地盤、メンテナンスなど、さまざまな要素を考慮する必要があります。
本記事で紹介した7つの特徴を参考に、地震に強い家を建てるための知識を深めてください。
地震はいつ起きるかわかりません。
大切な家族を守るために、地震に強い家を検討しましょう。

 0799-24-0558
0799-24-0558
 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
 ご来店予約
ご来店予約
 モデルハウス見学
モデルハウス見学





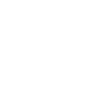


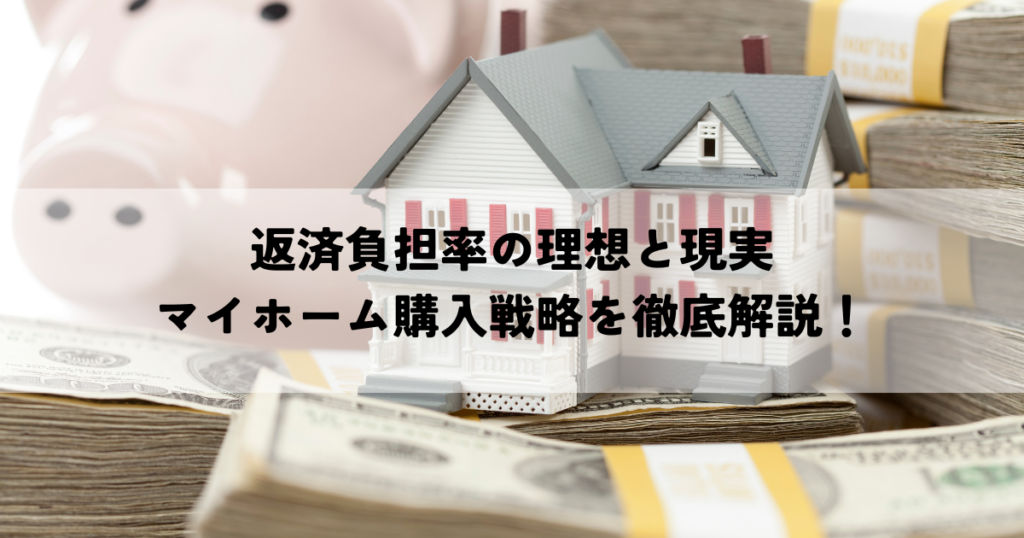
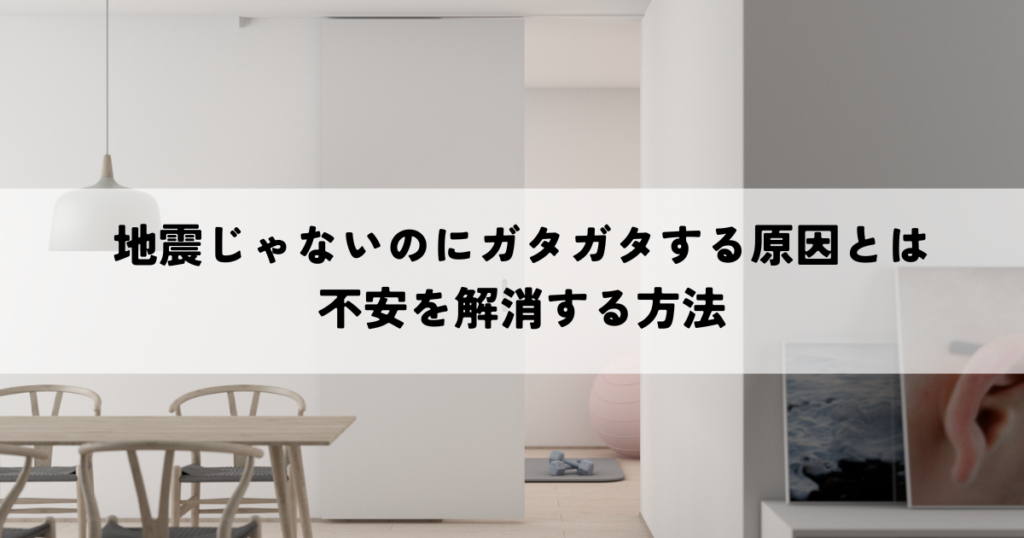
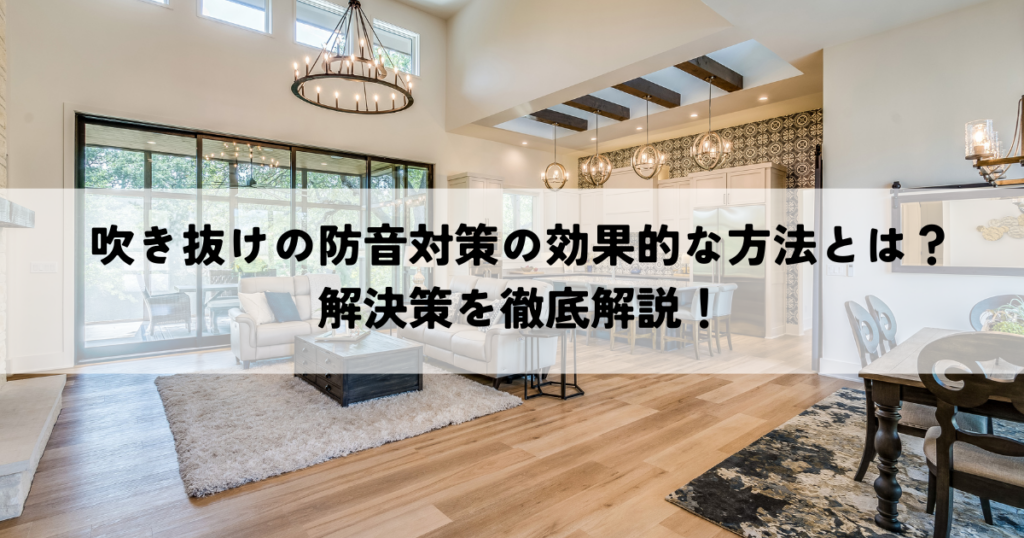
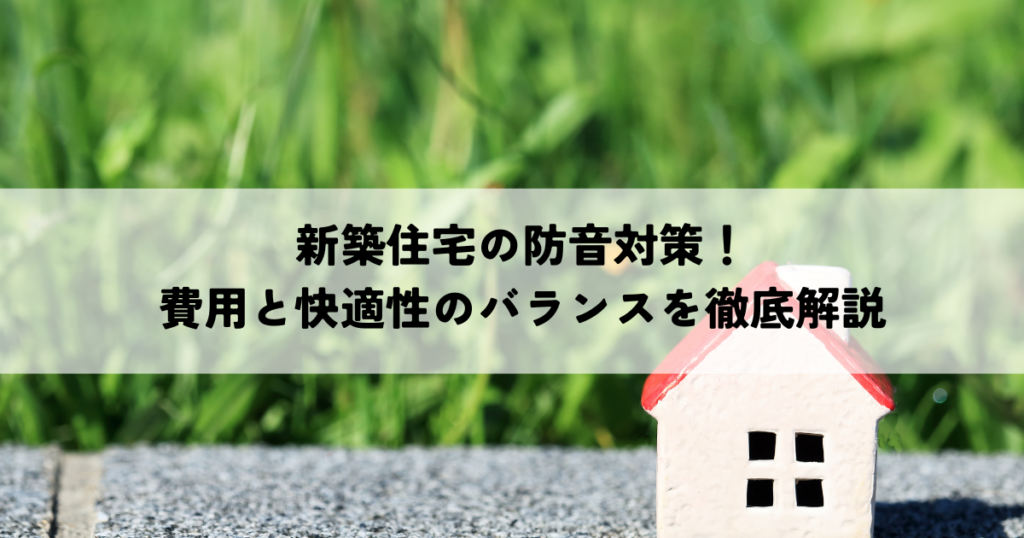

 イベント情報
イベント情報
 資料請求
資料請求
 お電話で
お電話で