玄関を彩る小さな段差である上がり框は新築やリフォームを検討する中で、その存在は意外と大きな課題となるかもしれません。
高さや素材、形状などのさまざまな選択肢があり、迷ってしまうのも当然です。
今回は、上がり框の役割から選び方のポイントまで、分かりやすくご紹介します。
高齢者への配慮についても触れながら、快適で安全な玄関づくりに役立つ情報を提供します。
ぜひ最後までお読みください。
上がり框とは何か
上がり框の定義と名称
上がり框とは、玄関と室内の床を区切る段差部分に設けられた板のことです。
玄関框(げんかんかまち)と呼ばれることもあります。
これは、靴を脱いで室内に入る日本の住宅文化に深く根ざした要素であり、土間と居住空間を明確に分ける役割を担っています。
上がり框の歴史と日本の住宅における役割
古くから、上がり框は単なる段差以上の意味を持っていました。
かつては、訪問客とのコミュニケーションの場としても利用され、内外空間の明確な区切りだけでなく、人々の交流を促す文化的役割も担っていたのです。
現代の住宅でも、その機能性とデザイン性は大切にされています。
上がり框の機能的な役割 土砂の侵入防止と休憩スペースとしての利用
上がり框は、靴底に付着した土砂やホコリが室内に浸入するのを防ぐという重要な機能を持っています。
また、靴の脱ぎ履きをする際の休憩スペースとしても活用でき、特に高齢者や小さなお子さんにとって便利です。
上がり框の文化的役割 内外空間の区切りとコミュニケーションの場
上がり框は、家と外の世界を隔てる境界線として、視覚的にも空間を区切ります。
同時に、昔ながらの日本の住宅では、そこで近隣住民との簡単なコミュニケーションが生まれる場でもありました。
上がり框の高さ・素材・形状選びのポイント
上がり框の高さの目安とバリアフリーへの配慮
上がり框の高さは、一般的に15~18cm程度が推奨されています。
これは、バリアフリーの観点から、高齢者や体の不自由な方が安全に利用できる高さです。
しかし、住宅の構造や家族構成、ライフスタイルによって最適な高さは異なり、場合によってはもっと低い高さや、逆に高めの高さを選ぶこともあります。
高齢者や車椅子利用者のいる家庭では、極力段差を少なくすることが重要になります。
素材選びのポイント 耐久性とデザイン性の両立
上がり框の素材は、木材、石材、タイルなど様々な選択肢があります。
それぞれに耐久性やデザイン性、メンテナンスの容易さなどが異なります。
玄関全体のデザインや雰囲気、そして予算などを考慮して、最適な素材を選びましょう。
木材は温かみのある雰囲気、石材は高級感、タイルは多様なデザイン性を提供します。
形状の種類と選び方 玄関の広さや動線との関係性
上がり框の形状には、直線型、L字型、コの字型、斜線型、曲線型などがあります。
形状は、玄関の広さ、収納スペース、動線などを考慮して選ぶ必要があります。
例えば、狭い玄関では斜め型が空間を広く見せる効果があります。
一方で、広い玄関では、L字型やコの字型によって、複数の出入り口を確保することも可能です。
上がり框がない場合のメリットとデメリット
上がり框がない玄関は、バリアフリー化に最適で、空間を広く見せる効果があります。
しかし、土砂やホコリが室内に入り込みやすくなるというデメリットも考慮する必要があります。
掃除の手間が増えることや、防犯上の懸念も考えられます。
高齢者や体の不自由な人のための工夫 手すりや式台などの設置
高齢者や体の不自由な方が安全に玄関を利用できるように、手すりや式台、ベンチなどの設置を検討しましょう。
1:手すり
昇降時の補助として有効です。
2:式台
段差を低くすることで、昇降を容易にします。
3:ベンチ
靴の脱ぎ履きや休憩に役立ちます。
これらの設置位置や高さは、利用者の身長や体格に合わせて調整することが重要です。
まとめ
この記事では、上がり框の役割、高さ、素材、形状、そして高齢者への配慮について解説しました。
上がり框は、単なる段差ではなく、玄関の機能性とデザイン性を高める重要な要素です。
新築やリフォームの際には、家族構成やライフスタイル、そしてバリアフリーの観点などを考慮し、最適な上がり框を選びましょう。
安全で快適な玄関空間を実現するために、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。
快適な住まいづくりに向けて、ぜひご検討ください。


 0799-24-0558
0799-24-0558
 メールでのお問い合わせ
メールでのお問い合わせ
 ご来店予約
ご来店予約
 モデルハウス見学
モデルハウス見学




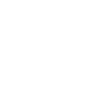




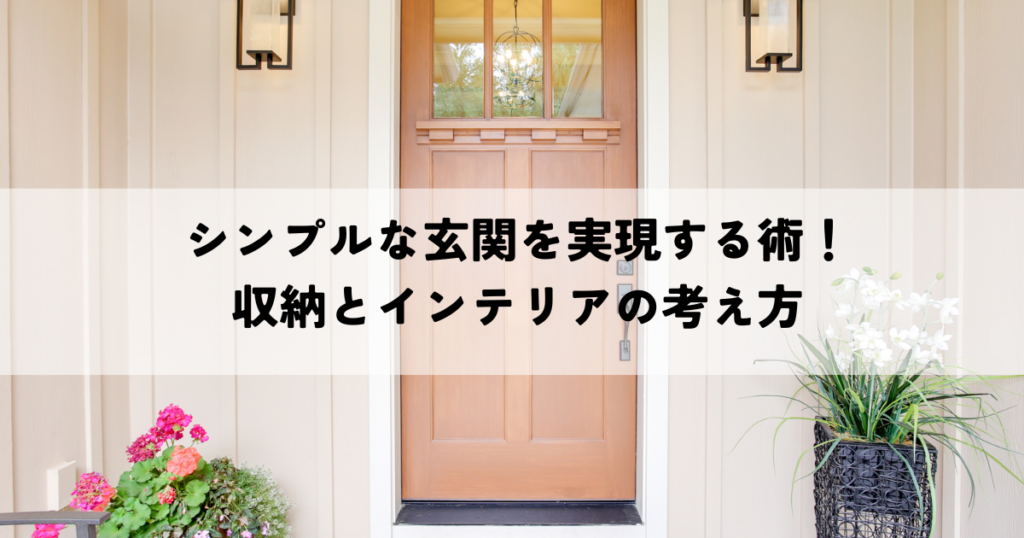

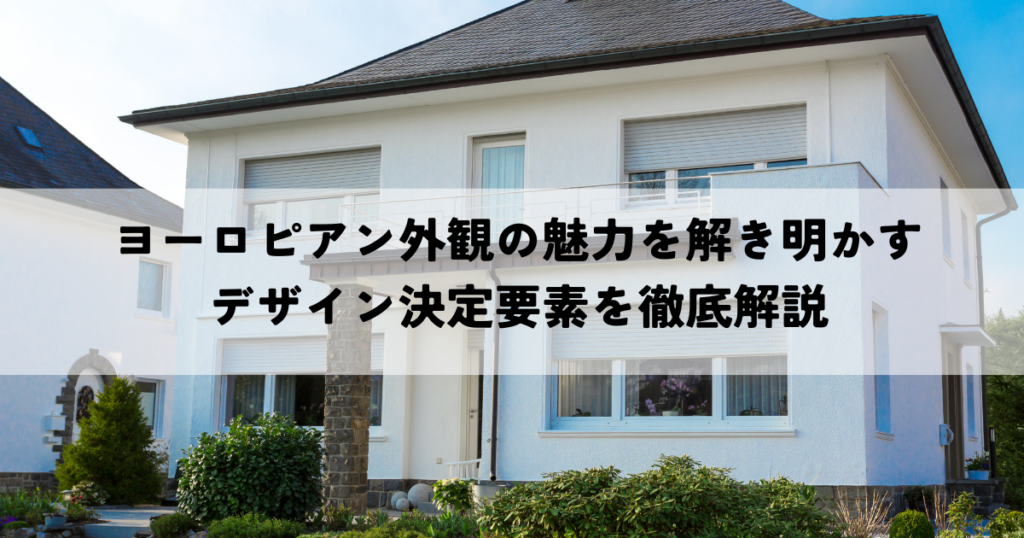
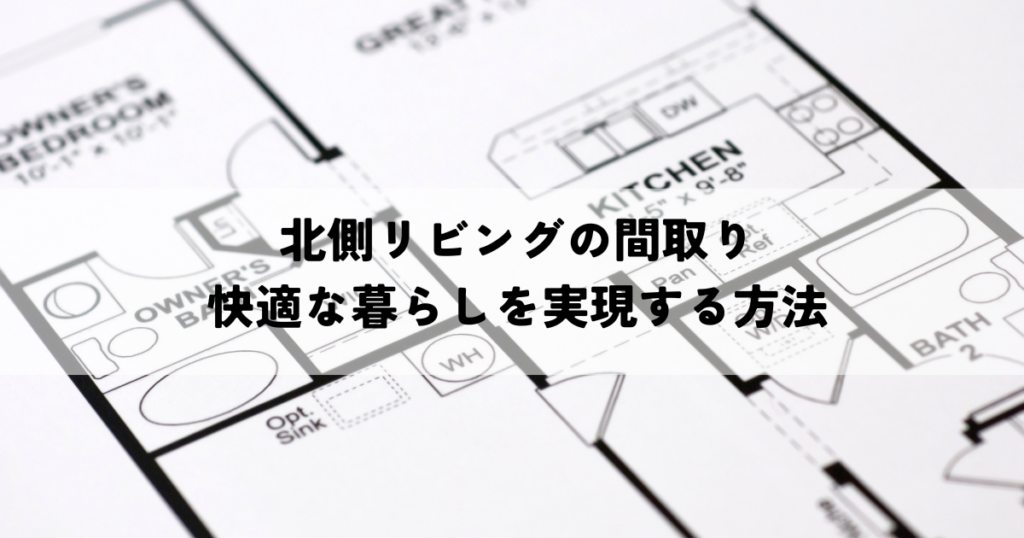


 イベント情報
イベント情報
 資料請求
資料請求
 お電話で
お電話で